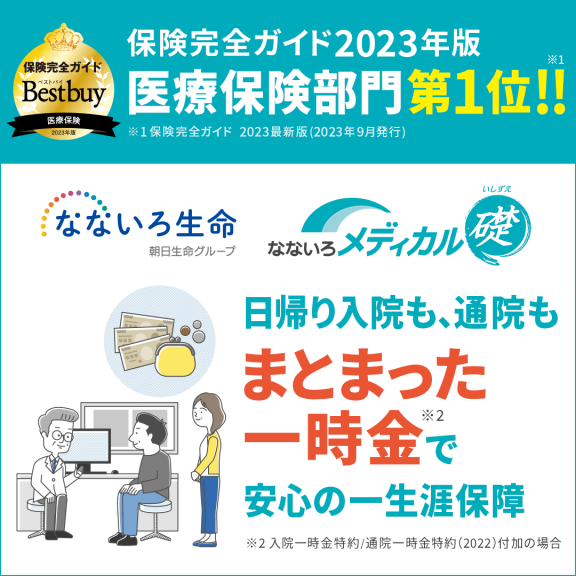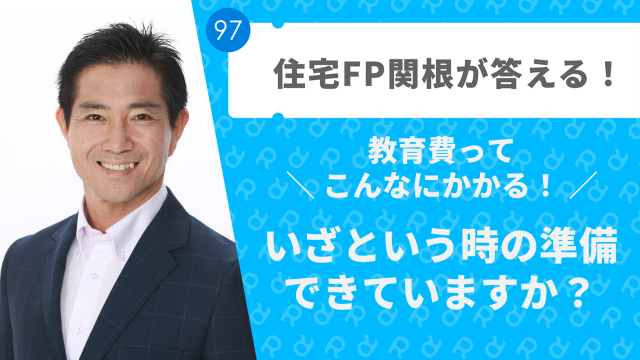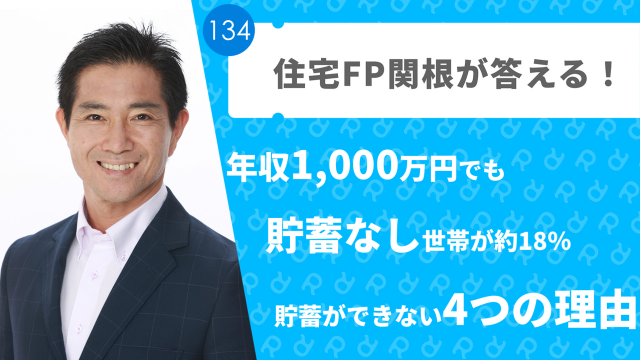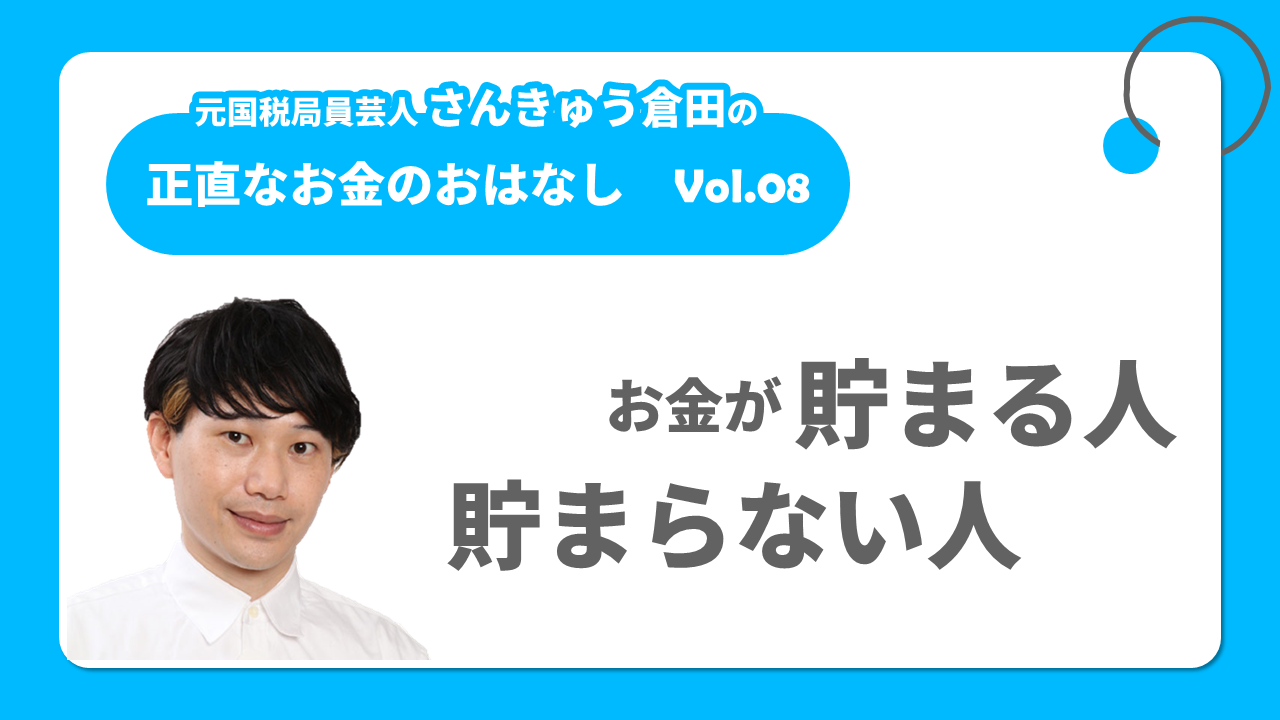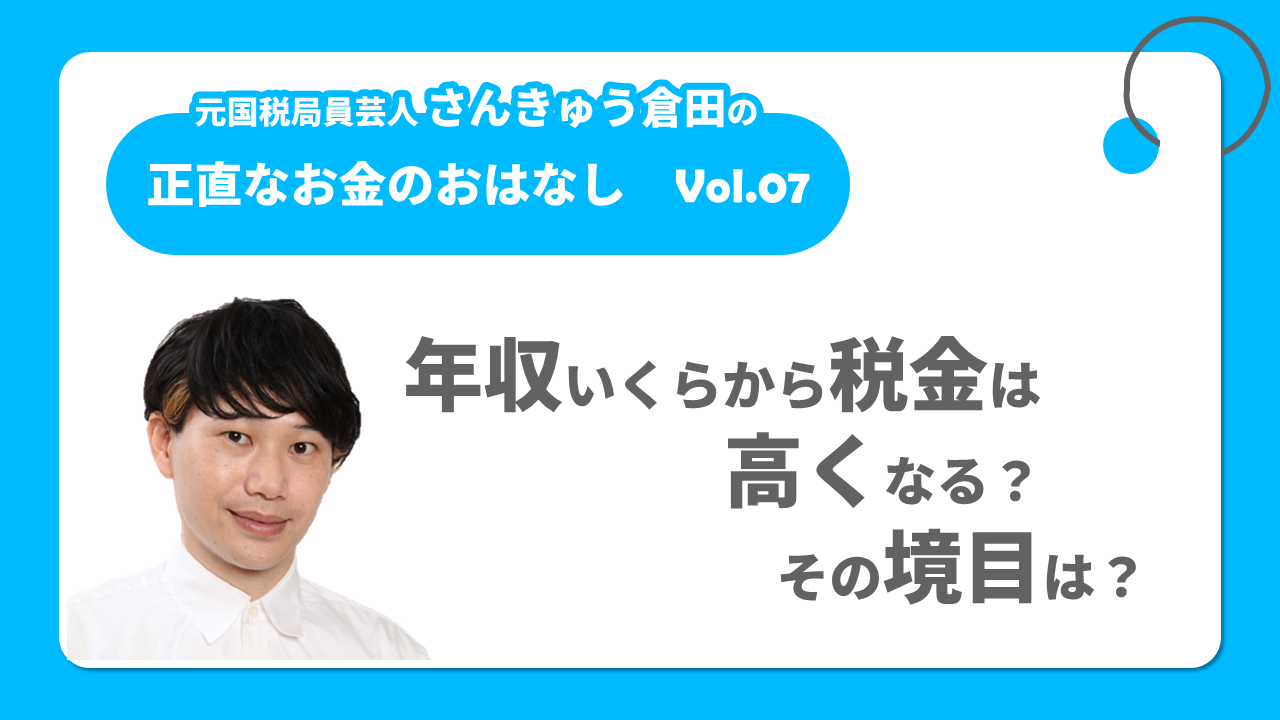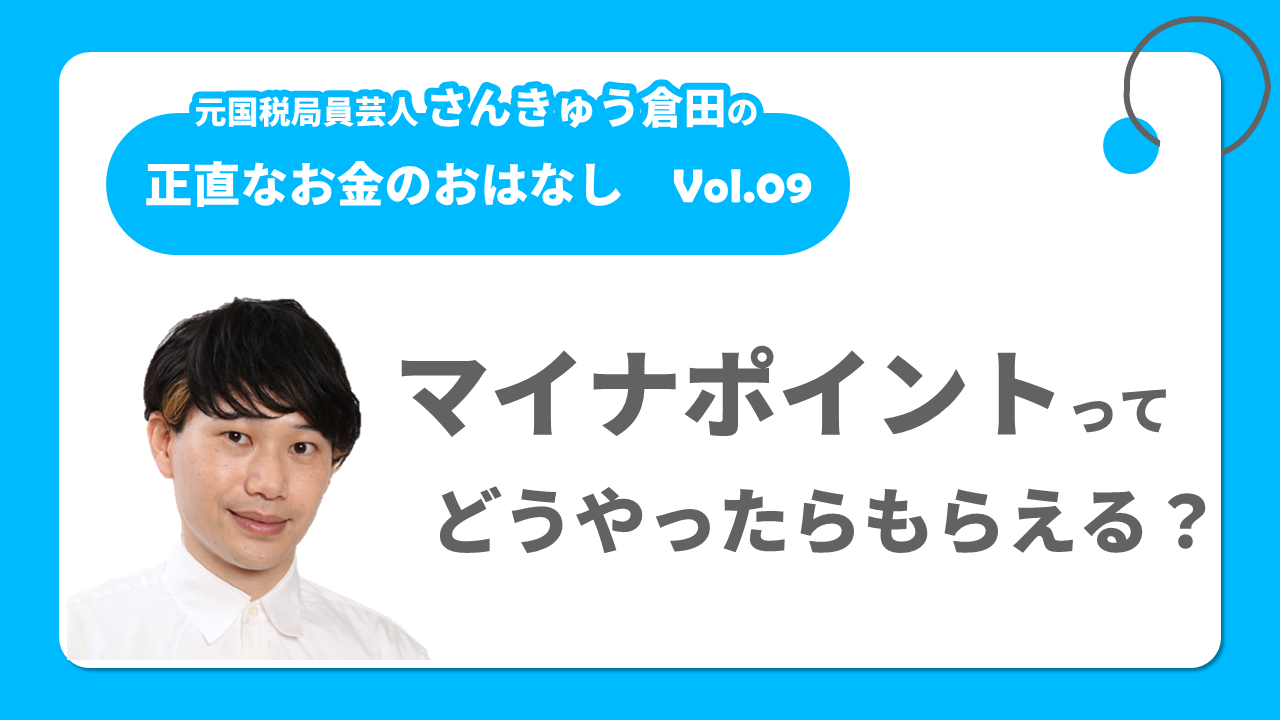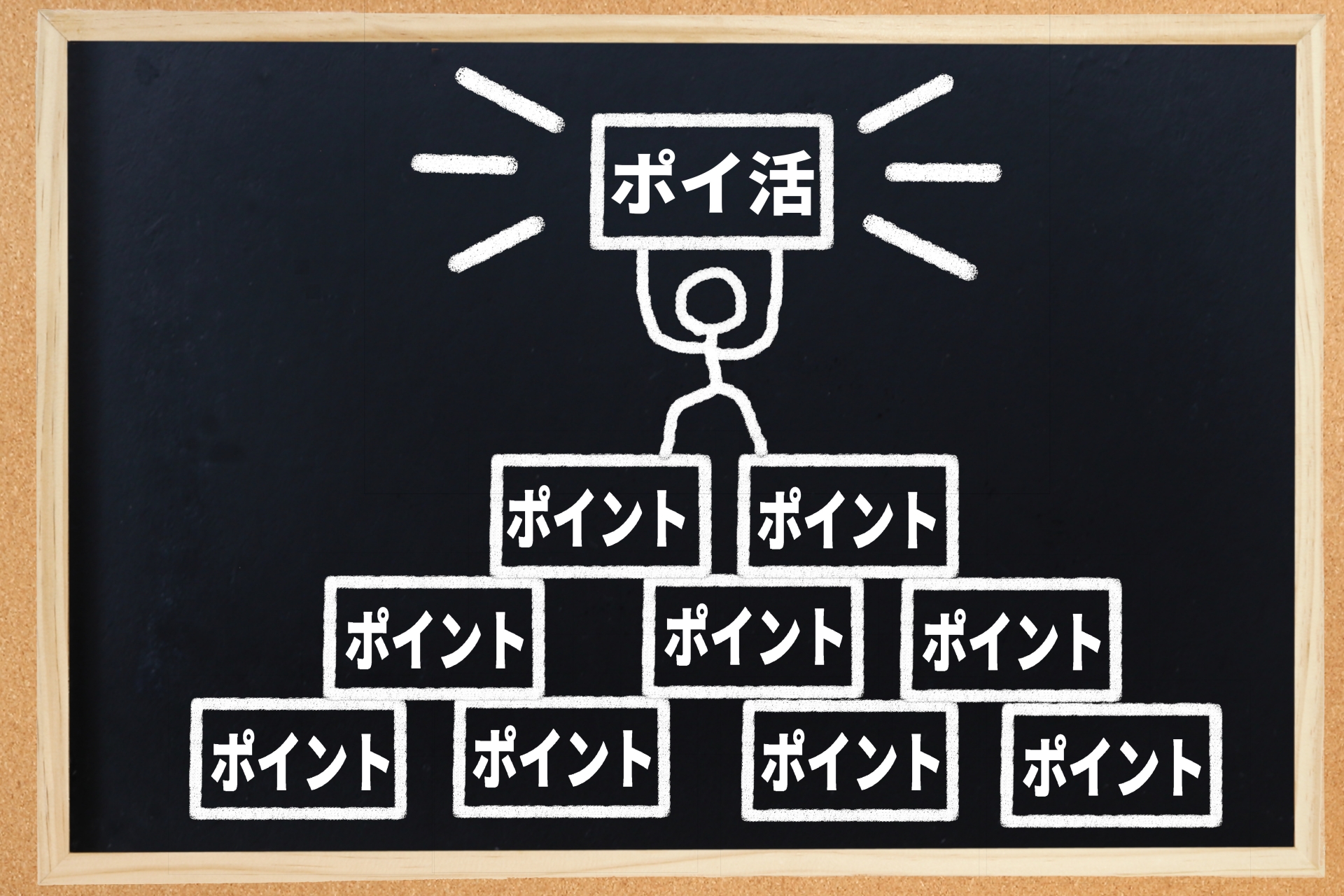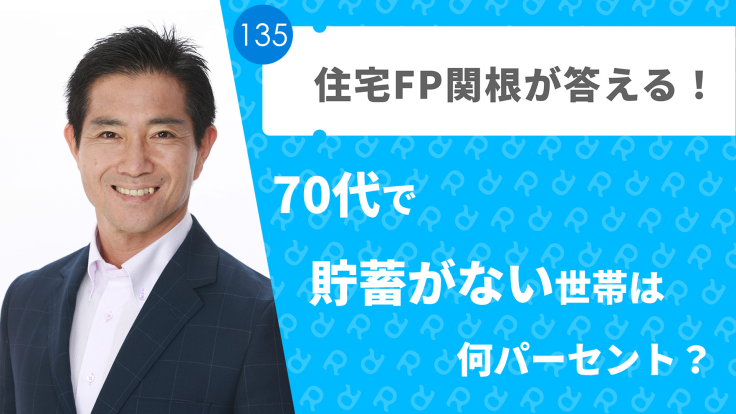
著名人・専門家コラム
2025.02.12
70代で貯蓄がない世帯は何パーセント?【住宅FP関根が答える!Vol.135】
みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。
前回のコラムでは年収1000万円以上あるのに貯蓄ができない人についてお話してきました。しかし、この貯蓄がないという問題、実はほかでも同じように問題になっています。今回のコラムでは老後に向けての資産形成についてお話していきたいと思います。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」によると、70代の金融資産保有額【二人以上世帯】(※金融資産非保有世帯を含む)は、平均1,757万円、中央値700万円ということでした。資産にかなり余裕がある世帯が一定割合いるということと、この中央値である700万円が実態に近いと言えるでしょう。
そして70代以上・二人以上世帯「金融資産保有額」の分布が以下の通りです。
- 金融資産非保有:19.2%
- 100万円未満:5.6%
- 100~200万円未満:5.1%
- 200~300万円未満:4.3%
- 300~400万円未満:4.7%
- 400~500万円未満:2.5%
100~500万円未満が16.6%、100万円未満、金融資産非保有も合わせると全体の41.4%に該当します。続きを見ていきます。
- 500~700万円未満:6.2%
- 700~1,000万円未満:5.8%
500~1,000万円未満が12%となります。つまり、大きなくくりにはなりますが、まったく貯蓄のない金融資産非保有から1,000万円未満までを合わせると53.1%となり、70代の約半分が該当します。さらに見ていきます。
- 1,000~2,000万円未満:16.8%
- 2,000~3,000万円未満:7.4%
- 3,000万円以上:19.7%
1,000万円以上で約半分の方が該当します。近年では老後2,000万円問題という言葉が流行りましたが、3,000万円必要だともいわれています。なぜ3,000万円かというと、毎月7万円で公的年金と合わせて約35年間暮らすことができるからです。仮に65歳から預貯金を取り崩すとして、90歳までで3,000万円あると安心だよねという一つの指標になっていました。
そこで考えたいのが現実の世の中の金融資産額です。70歳ということなので、ここでは仮に75歳時点の数字だったとします。65歳から取り崩しが始まったとして、75歳までの10年間、つまり120か月を毎月7万円だとすると840万円すでに切り崩していることになります。65歳時点で3,000万円あったとすると、本来なら手元に2,000万円以上、保有しておきたいところです。しかしながら現実は、70代で2,000万円以上ある家庭は約30%、おおよそ3人に1人しかいません。
なんとかお金をためていきたいところではありますが若いころは年収が少ないため、年収が上がってから貯蓄を頑張ろうと思う方も多いですが、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」では年齢が上がるほど貯蓄ペースは落ちるという裏付けがされています。
こちらの調査で、手取りから貯蓄に回す割合は以下の通りです。
- 20代、30代で手取りの14.0%
- 40代、50代で手取りの12.0%
- 60代、70代で手取りの9.5%
しかしこれは、手取り額の何パーセントなのかという調査です。若いうちの手取り20万円の14%は28,000円、一方、50代で手取り50万円あった場合、貯蓄にまわせる12%は60,000円です。
年を追うごとに、子どもの学費もかかってきます。「年収があがってから貯蓄額を上げよう」と思っている方は楽観視せず、人生を長い目で見て今から行動することを強くお勧めします。
※参考:家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)|金融広報中央委員会
年齢を重ねてから貯蓄がないというのはかなり厳しいです。物価が上がっていくにつれて年金が上がればいいですが、日本の年金制度では上がらない仕組みになっています。そう考えると、物価が上がって一番困るのは貯蓄を切り崩している年金暮らしの高齢者です。バブルのころは貯金をしていればお金が増えましたが今はまったく社会構造が違います。
2022年の年金受給額は減ってしまう予定です。そして近年ご存じの通り、輸入品を中心に物価は上がりやすい傾向にあります。老後の唯一の収入減と言える年金は減り、預貯金を預けていてもお金は増えません。
以前、年金は60歳から受け取ることができましたが、それがだんだんと後ろにずれ込み、今後は65歳からとなります。しかし今の若い人たちが年金を受け取るころには68歳など、さらに後ろにずれ込むこともあると予想されます。
一昔前の日本は高度経済成長、バブルと景気は成長し続けるものだと思われていました。バブルがはじけた経験がなかったからです。子どもの数もたくさんいました。それが、バブルがはじけ、やっと経済が回復しても賃金は上がらない、金利を上げることもできなくなってしまいました。
人生は計画通りにはいきません。老後2,000万円、3,000万円必要だといっていてもそれだけ持っている人は半分もいません。預貯金を切り崩しながらの生活はやはり厳しく、何と言っても精神的に不安が増してしまいます。これからの時代、お金のことは自己責任の時代です。しっかりとした資産形成が重要なのはもちろんですが、貯蓄できるのは若い時と、教育費が終了した後です。教育費が終わる時期は、年収が高いことが多いのでもう一度貯めるタイミングがくることが多いです。
しかし最近は晩婚の方が増えていて、教育費が終わった後にもう一度お金を貯めるタイミングがないご家庭も多いです。そういったことを考えると、やはり若いうちから意識高く貯蓄をすることが非常に重要です。新NISAを利用して投資信託を行ったりすることで、あればあるだけ使ってしまうということも防ぐことができます。
また、生命保険を利用した資産形成もお勧めいたします。終身保険や変額保険、個人年金保険や養老保険といった、貯蓄機能を持つ商品を契約する方法です。本来の保険としての保障はもちろんのこと、支払った保険料の一部を保険会社に運用してもらうことで、将来の資産形成を期待することができます。
旧NISAから新NISAへと変化したのは、これからの資産形成は自己責任だと国が言っているということです。新NISAの活用、生命保険の活用、今一度、老後の資産形成についてしっかり考えてみてはいかがでしょうか。
WRITER’S PROFILE
㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直
ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。