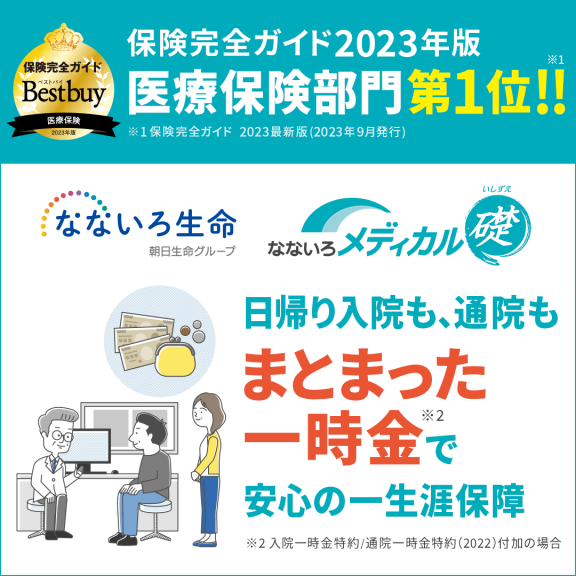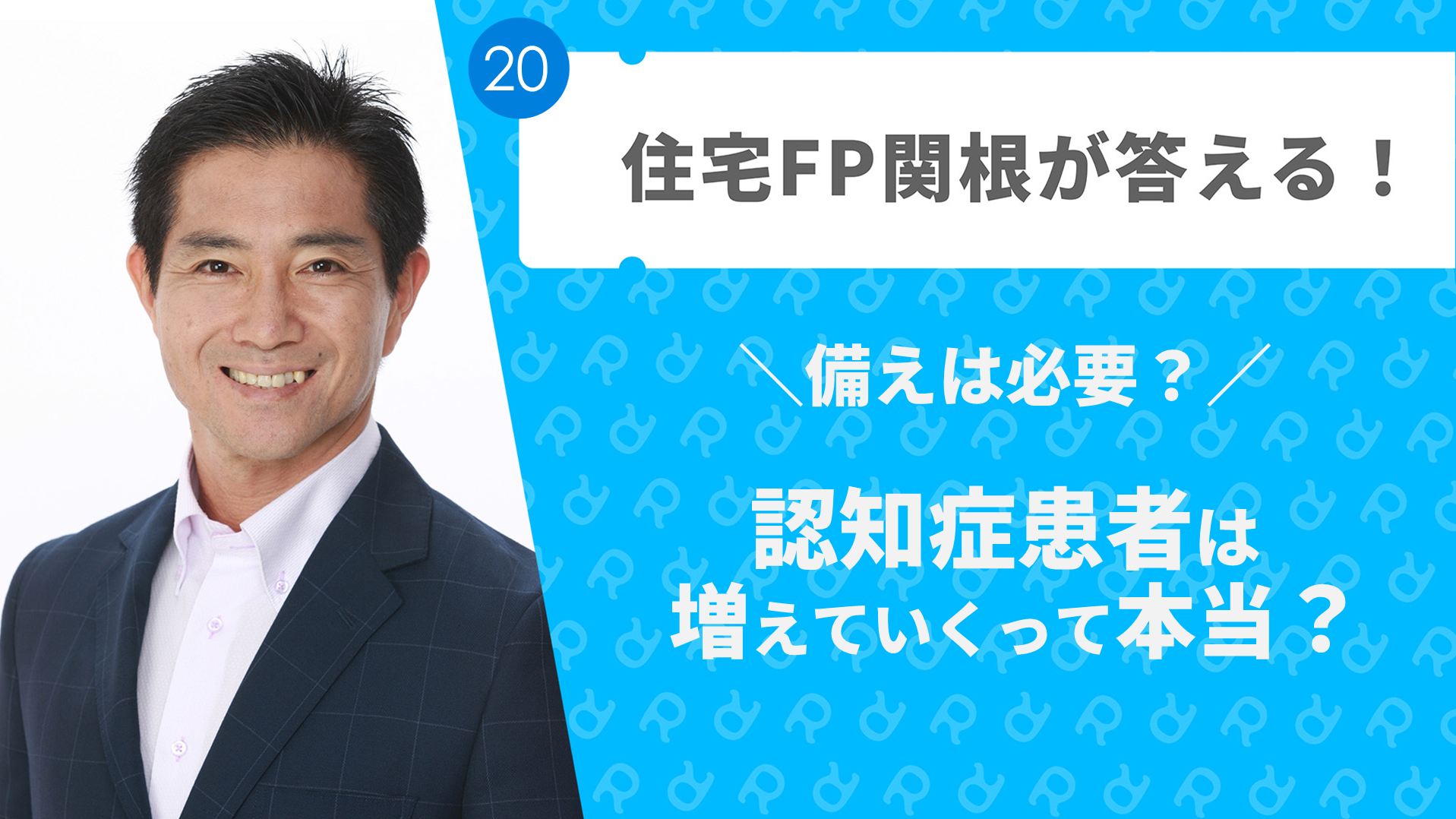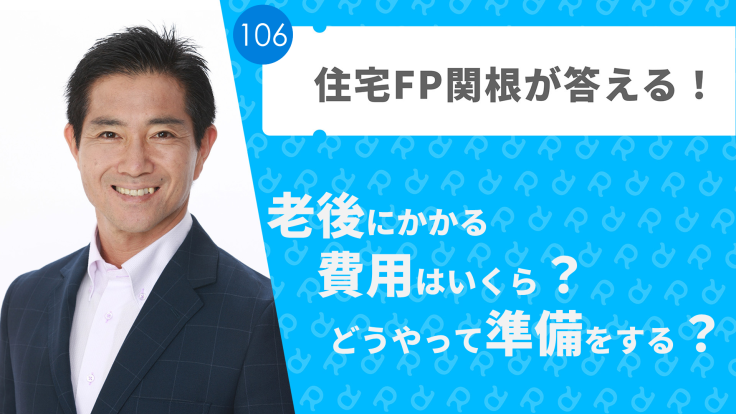
著名人・専門家コラム
2024.06.27
老後にかかる費用はいくら?どうやって準備をする?【住宅FP関根が答える!Vol.106】
みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。
長く生命保険の募集人をやっていると感じることが多いのですが、保険は万一お亡くなりになってしまったときの「死亡リスク」に備えるために加入するイメージが強いということです。しかし人生には、「死亡リスク」と同時に「長生きリスク」というものもあります。
日本の雇用環境において徐々に年功序列、終身雇用は崩壊しつつあり、以前と比べて雇用環境が不安定になりつつあります。
また将来の年金不安も感じる日本ですが、日本は世界一の長寿国でもあり、老後にかかる費用は生きている間一生涯かかります。老後資金はいくらぐらいかかるのかを把握し、長生きしたとしても耐えられる準備をしていきたいところです。
生命保険文化センターが2022年度に行った調査によると、夫婦2人で老後生活を送る場合に必要とされる最低日常生活費は月額で平均23.2万円となっています。ただこの23.2万円というのは最低日常生活費、つまり生きていくために最低限必要な金額で、趣味や旅行、外食や子どもや孫たちと楽しむ費用は含まれておりません。
老後、趣味や子どもたちとの交流などを楽しみながら生活を送るために必要な生活費、ゆとりある老後生活費は平均で14.8万円の上乗せが必要となっています。そのため、ゆとりある老後の必要生活費は月額で38万円となります。
※参考:2022(令和4)年度 生活保障に関する調査|公益財団法人生命保険文化センター
ゆとりある老後の生活費が38万円と分かったところで、老後の収入はいくらくらい期待できるのでしょうか。老後の収入源というと公的年金が中心となります。厚生労働省年金局の統計によると、平均的な収入で40年間就労した夫と40年間専業主婦だった妻というモデルケースで公的年金額は月額23万円程度とされています。
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)の給付水準
※参考:令和6年4月分からの年金額|日本年金機構
このデータを元にゆとりある生活を送るために必要な費用を計算します。
38万円(ゆとりある生活費)- 23万円(年金収入)=15万円
上記のように老後、ゆとりある生活を送るためには毎月15万円の取り崩しが必要だということが分かります。仮に65歳から90歳まで25年間、毎月15万円を取り崩した場合、65歳地点で必要な預貯金額はいくらくらいになるの計算します。
25年間×12か月×15万円=4,500万円
上記のように老後ゆとりある生活を送るためには65歳時点で4,500万円が必要ということになります。
ただ、この数字は日々の生活費のみの数字です。長い人生なにが起こるかわかりません。病気になることもあるかもしれませんし、不意な支出も考えられます。
大きな支出として多いパターンは、建設から年数が経っている家のリフォームなどが多いです。例えば、40歳の時に建てた家が30年経ち、大掛かりなリフォームを組まなければいけなくなるとした場合、年齢は70歳になります。老後、年金生活を送る中で数100万円単位の住宅のリフォームをしなければいけなくなった場合などは、大変多くの費用が必要になってきます。
数年前に老後2,000万円問題という言葉が流行りましたが、ゆとりある生活を送り続けるためには、さらに多くの資金を準備しておく必要があります。
それでは、老後資金を貯めるためにはどういったやり方があるのでしょうか。やはり資産形成の中心にあるのは投資になると思います。2024年に入り、政府が少額投資非課税制度(NISA)の投資枠を大きく増やし、積み立て枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円、そして投資上限額として合計で1,800万円となりました。こういった制度をうまく活用し、さらに個人型確定拠出年金(iDeCo)など、資産形成をサポートする制度を利用しながら積立をすることをお勧めします。
またこういった非課税制度を活用した投資と並行して考えたいのは、保険による積立です。最近、NISAなどの投資環境が整備された分、悪くいわれることが多くなった外貨建て保険ですが、投資冥利はあると考えています。外貨建て保険も賢く使えばリスク分散をしながら効率よく運用の手助けをしてくれる大変有効な商品です。
NISAなどの投資商品は、投資をしている本人が早いタイミングでお亡くなりになってしまった場合、元本が十分に増えていない可能性もありますが、保険による積立の場合、本来の生命保険の仕組みを利用することができます。そのため契約期間中にお亡くなりになった場合、掛け金に対して大きな死亡保険金(リターン)を得ることができます。また毎月の保険料は生命保険料控除の対象にもなりますし、月々の保険料の一定額を所得から控除することも可能です。
ただ一方で外貨建て保険の場合、外貨建てで保険料を支払い、外貨建てで死亡保険金や解約返戻金を受け取ることになるため、直接為替によるリスクを受けることとなります。解約のタイミングや、死亡保険金を受け取るタイミングで円高が進んでいった場合、当初計算していたリターンを得られない可能性もあるため、そういったリスクも理解したうえで契約に進んでいただけたらと思います。
WRITER’S PROFILE
㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直
ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。