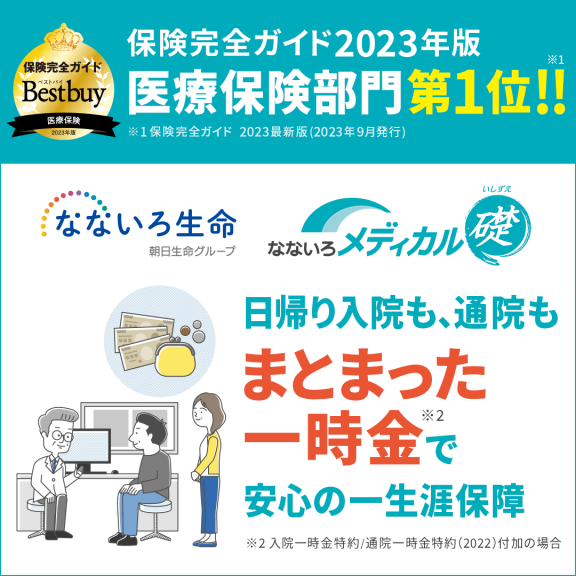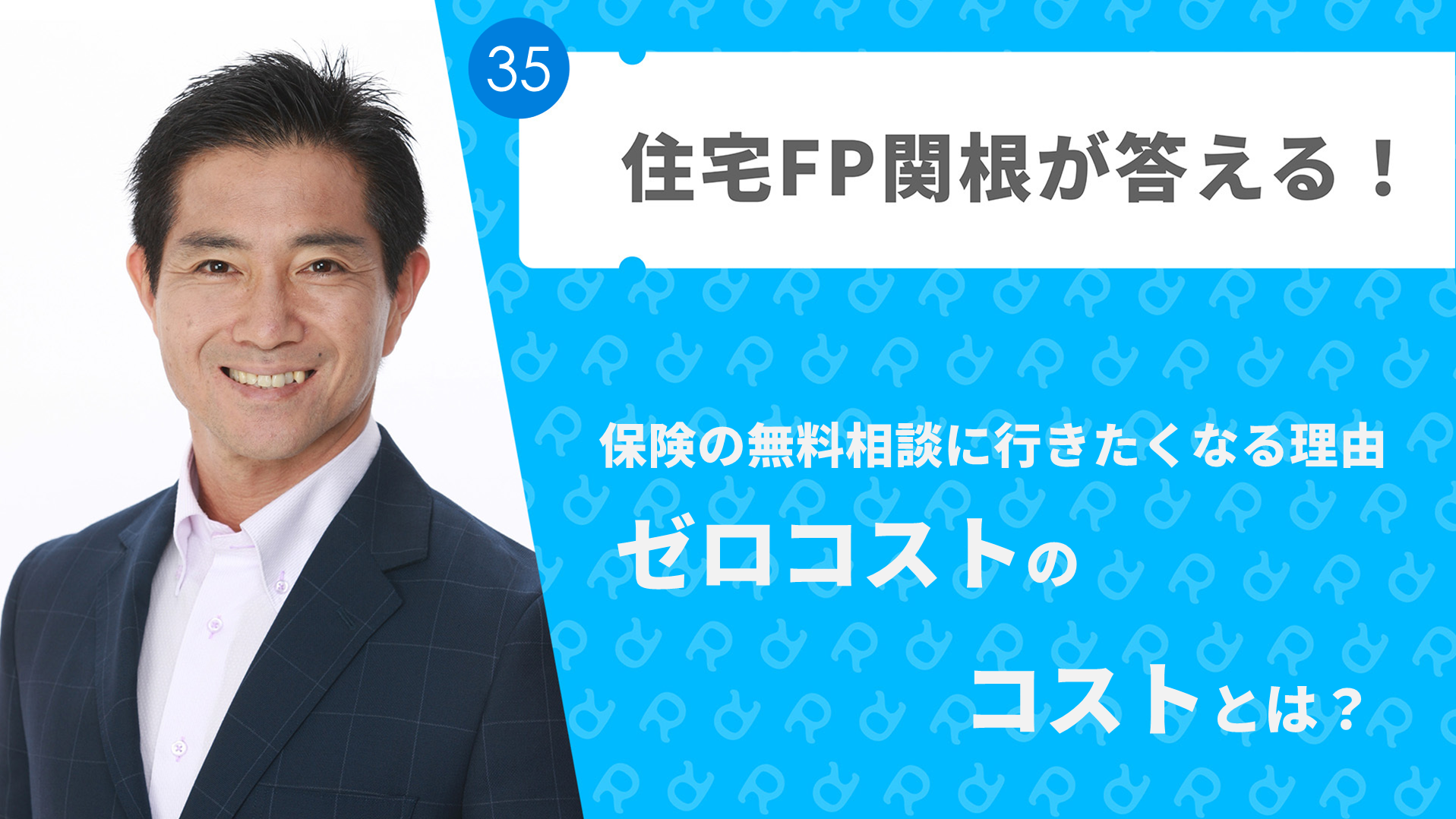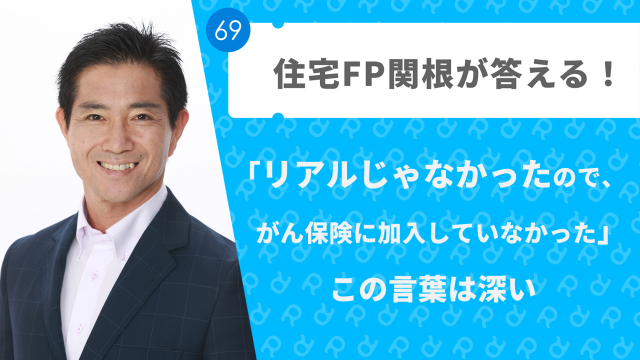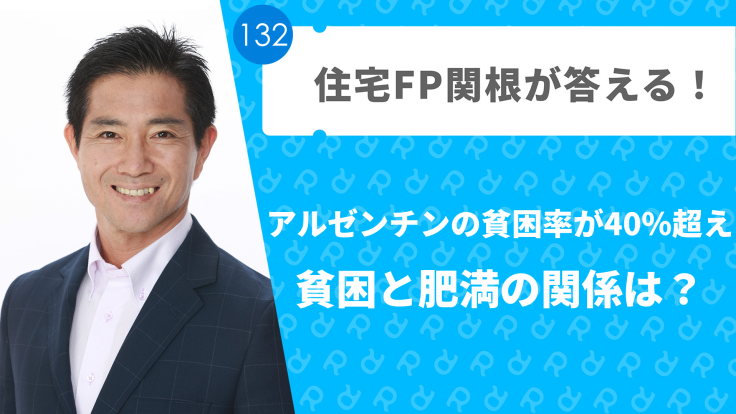
著名人・専門家コラム
2025.01.17
アルゼンチンの貧困率が50%超え、貧困と肥満の関係は?【住宅FP関根が答える!Vol.132】
みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。前回のコラムですべての健康は食事からということで、栄養バランスの整った配食サービスは健康にも、食事の制限にも利用しやすいというお話をしました。今回のコラムでは前回お話した健康は食事からであるということがよりわかる出来事についてお話していきたいと思います。
今回のお話は昨年のアルゼンチンの消費者物価指数が前年同月比2.4倍に上昇したときの出来事です。消費者物価指数とは物価を表す指数というお話をしましたが、前年同月比2.4倍というのはスーパーインフレが起こっているということです。アルゼンチンの消費者物価指数は以前、1991年にも2.4倍になっていました。それ以来、32年ぶりに大きく上昇しました。アルゼンチンでは、通貨ペソが暴落し、通貨自体の信用が、落ちてしまいました。
※参考:World Economic Outlook Database|IMF
アルゼンチンでは、2001年に国債の金利が払えなくなり、デフォルト(債務不履行)を起こしています。そのためアルゼンチンの人々は、最低限の生活費はペソで所有していますが、将来に向けた資産、貯金などは米ドルで持っています。しかし、この人々の動きはアルゼンチンとしては困った状況で、自国のペソが売られ、ドルが買われてしまうとペソ安が進んでしまいます。
そのためアルゼンチンでは、ペソを売るために一定の規制がかけられていました。その規制の甲斐もあり、一定割合、ペソが売られるのを抑制されていました。しかしながら、ペソの信頼があまりにも低くなってしまったことによって、政府としてもその規制を緩めざるをえなくなってしまいました。これにより、そもそも信用の薄かったペソの、「売り」に拍車がかかっている状況です。そんな中での、アメリカFRBによる利上げにより、信用の低いペソを売って、利回りの良い、ドルを買いましょうという流れが定着しました。
2022年は1ドル、約160ペソ、2023年は1ドル、約350ペソ、そして現在は1ドル、約1,000ペソとたった1・2年で信じられないペソ安となっています。しかしペソを売って、ドルに変えるには、障壁があったため、闇レートでドルに交換されていました。そのため、アルゼンチン・ペソは公式レートとは別に、闇レートでの取引があり、実際にはもっと多くのペソが必要になってしまうというのが現状です。いずれにせよ、正式なルートの相場からも分かるように、相当なペソ安が続いているのは間違いないと言えます。
そもそもですが、多くの国で物価全体が押し上げられています。世界的な異常気象などで、穀物の価格が上がり、エネルギー需給の崩れで、エネルギー価格も上がり、畜産の価格も上がっています。そんな中での、ペソ安で輸入物価も上がってしまいます。
物価は1年間で、2.4倍になっています。本来、その分賃金が上がればいいのですが、残念ながらそうもいかず、政府、労働組合、経営者団体で話し合い、最低賃金を26%引き上げることで合意しています。ここから貧困層が一気に増えてしまい、貧困率は驚異の52.9%となりました。6年前の2018年上半期には、約27%だったことを考えると危機的な状況です。
そして問題は、貧困層の中でも、極貧率の割合が18.1%にも達しているということです。
困窮する市民のために、市民団体が食材の配給をやっていて、市民が列をなして配給に並んでいるというニュース映像を見て感じた違和感がありました。
配給の列に並んでいる人たちが総じてかなりの肥満体型であるということです。肥満と飢餓には、深い関係があります。現在は、飢餓に苦しむ人々が増える一方で、肥満に悩む人もまた増加していると国連の食糧農業機関(FAO)が発表していました。
肥満率が一番高いのはアメリカです。これはなんとなく想像がつくかと思いますが、途上国での肥満は不思議だと思いませんか。発展途上国には飢餓の人がたくさん存在し、同時に肥満の人もたくさん存在しています。
貧困と、肥満、正反対に見えるこれら二つの問題は、なぜ起こるのでしょうか。いろいろと理由はあるのですが、まず新鮮な食べ物は価格が高いということです。一方で、価格の安いものは糖質や脂質が多く、ごはんやパン、砂糖などを多く使ったものが多いです。こういった食事は栄養の偏りが見られ、太りやすくなってしまいます。
日本人は栄養バランスが考えられた、給食もありますし、家庭科の授業で、栄養の基本的な勉強も行い栄養意識も高いですが、発展途上国になると栄養学の意識も低く、栄養バランスの取れた食事をしようという気持ちよりも安価でおなか一杯にしようという感覚に走りがちです。
厚生労働省が発表している「国民健康・栄養調査」というデータによると、低所得世帯は、高所得世帯に比べて、肉や野菜の摂取が少なく、穀物の摂取が多い、全体として栄養バランスが取れていない傾向にあることがわかります。
アメリカでたびたび出てくる数値、ジニ係数は、どれくらい所得や資産が平等に分配されているのかを表している、要するに貧富の差を表す数値です。アメリカが40位で、日本は111位となっています。
※参考:ジニ係数|世界銀行
アメリカの平均寿命は2021年時点で76.1歳と、1996年以来の低水準に落ち込んでいます。
※参考:Provisional Life Expectancy Estimates for 2021|NCHS
本来なら医療の発達や生活レベルの向上で死亡率は下がっていきます。実際に、先進国、すべての国において、10万人当たりの死亡率は下がっています。しかしながらアメリカだけは、近年死亡率が上がっています。
所得格差に苦しむ人々は栄養バランスなんて考えずジャンクフードを食べ、酒におぼれ、不健康に太っていき、依存性の高い鎮痛剤をゲートドラッグとして、薬物中毒に落ちていく、そして若くして、亡くなってしまう方も増えています。
貧困と肥満、貧困と喫煙率、こういったものはすべてがリンクしています。健康と食事の関係はこういった事例からも分かりやすく具体的に考えられると思います。みなさん、まずは食事の改善から始めてみてはいかがでしょうか。
WRITER’S PROFILE
㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直
ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。